「飯場の暮らし」
平岡 清さん「飯場の暮らし」

平岡さんは昭和五年、宮下の生まれ。生まれた家は、昭和三十七年の水害以前は築堤がなかった双珠別川の川っぷちにあった。今もその場所のすぐ近くに暮らしている。平岡家が占冠村へ入植したのは明治、まごじいさんの浅蔵さんの時代だった。その頃占冠村の農家は、夏は農作業、冬は山仕事という家がほとんどで、平岡家もその一つである。高等小学校を卒業した十五の年の冬から、父の英吉さんにならって山仕事に入った。
平岡さんは最初の冬、山の中の飯場の「薪切り」をして飯場の空気に馴れ、次の年からは「馬追い」をした。最初は父親と同じ山に入ったが、父親は、怒るばっかりで教えてくれない。一週間で嫌になって別の飯場に入った。「そしたら一人では、やっぱりうまく積めない。吉田さんという馬追いが積むの黙ーって見てたよ。それで覚えたよ。」と笑う。
十七歳の時、自分の馬を買ってもらって、毎年冬には山に入った。馬がブルに代わったりウインチを使いだしたりと山仕事は次第に機械化していったが、四十五才くらいまで三十年近く続けた。
造材の仕事は十ニ月から四月、馬そりを使って材を運べる雪の時期だけ行われる。木を切り倒したらその場で枝を落として一定の長さに切りそろえ、馬が入れない木が混んだ所はトビという道具を使って人力で降ろし、馬が使える急な斜面は玉引き(やんちゃ引き)といわれる小さな馬そりで中腹の土場まで下す。ここからは大きなバチ引きといわれる馬そりで、川沿いの土場まで運ぶ。中腹の土場を作らずに、玉を二台つないで直接川沿いまで運ぶ「直送」という方法もあった。それぞれに役割が分担されており、木を切るのは「山子」もしくは「杣夫」、トビで木を出すのが「薮出し」、馬を使って丸太を運び出すのが「馬追い」、川沿いの土場で材を積んで整理するのが「土場まき」、これら山仕事全体を管理するのを「山頭」、そして材を川に流して運ぶのが「流送人」といった。このほかに飯場全体を管理する「飯場長」の下で、女の人が飯を炊き、「薪切り」や「薪運び」が薪を調達する。「てこ」といわれる雑用係は薪割りなどなんでもやった。
山の中腹、沢のある平らな所に飯場と馬屋は作られた。人夫だけでも四十人近い人数が生活する飯場は、中央が通り土間になっていて何箇所か火が焚かれており、左右に人夫たちが寝起する間がある。土に直接松葉を敷き、その上にむしろ、そしてその上に布団を敷いて寝た。吹雪くと雪が吹き込んでくるし、朝起きると布団のえりは息でがっちがちに凍っている。屋根は長柾で葺いてあるばかりで、春先屋根の雪が解ける頃は「むって、むって、どうもなんないんだよね。」という簡素な造りだった。
飯場での一日は、五時、まだ暗いうちから起きて馬にエサを食べさせるところから始まる。エサをやって馬具を取り付け、六時に自分も朝食をとり、七時にはそりを出して材を積みはじめる。下の土場まで午前中に一往復。昼を食べて午後にもう一往復すると、短い冬の日は落ちてしまう。十二、三人が一部屋で寝起きし、食事は、大きな縦長のおひつに入ったごはんと、バケツに入った味噌汁が運ばれてくる。おかずなどないので、それぞれが家から十日分くらいの煮物や漬け物を持参していた。どんぶりと箸も自分で用意したものだった。力仕事だから、一日三食で一升は食べた。戦中戦後の米のない時は、いもやとうきびばかり食べさせられた。夜は、飯場の外にある風呂で汗を流すとみんなむしろの上にごろりと横になって休む。中には焼酎をのむ人たちもあった。飯場ばかりを流れ歩いている人を「じゃこ」と呼んでおり、馬追いとの間では喧嘩も多かった。
戦時中の灯油のない頃は、何の油なのか寒くなると白く固まるような動物の油でランプを灯したが、黒い煙が出るので朝起きると顔が真っ黒になっていた。
この飯場の生活が冬の四か月間も続くのが、若い頃はいやでいやで、春にはすっかり飽きてしまって早く山を下りたかった。
春先に中州の丸太外しを手伝いに行った事がある。赤岩は流送の難所で、今にも増して大きな岩がゴロゴロとしていた。流送で引っ掛かった丸太が高さ七、八メートルにもなっている。これに数人が舟で近づき、丸太の上に飛び乗ってトビという道具を使って外していくのだが、あるきっかけで、ドドーッと全体が動き出す。これに巻き込まれると命はないので、動き出したらすばやく丸太の上を移動して舟に戻った。船頭は富山から来ていた専門の人で、十人以上も乗れるような大きな舟だった。
また、十七歳の時のこと、ニニウの流送人夫に食料を運んでくれと頼まれた父親は、二つ返事で引き受けておいて、「おい、お前行ってこい」とこう言うのだ。雨が降っていたので嫌な予感がしたが、仕方なく出かけることにした。中央からニニウへ向かう今の青巌橋のところに橋はなく、馬に乗ったまま川を渡る。行きは難無く渡れたが食料を届けて引き返して来てみると、降り続く雨でさらに増水していた。先輩馬追いの吉田さんの「絶対、水の流れに馬の横っ腹を向けるな、流れに逆らって斜めに進めば大丈夫だ。」という言葉を信じて後に続いたが、水は馬の背まで上がるほどで、あれは本当に恐ろしかった。
思えば、父には子どもの頃から仕事に出されたものだ。小学校五年生の冬、父親が山仕事で使う大きなトビを、そのトビを作った富良野の鍛冶屋で直してくるように言われた。鉄の部分だけでも一貫目(約四キロ)はある。
宮下から金山駅まで六里(約二十五キロ)を歩き、そこから汽車に乗って富良野へ。汽車に乗るのも、富良野へ行くのもその時が初めてのことだった。トビを打ち直してもらい、また汽車で金山へ戻って来た時にはすっかり日が暮れていた。辺りは暗いわ、トビを背負った肩は痛いわで、雪の上にでーんと座り込んだが、そうしていても始まらない。「遅くなるから、金山駅近くの舘内旅館に泊まって来い。」と宿代を持たされていたが、小学五年の子どものことだ、一人で知らない所に泊まるのがいやで、そのまま夜の雪道をまた歩いて帰って来た。家に着いたのは、夜中だった。
今でも納屋の中には、その時かついで行ったトビが大切にとってあった。丈夫そうな大きなトビだ。持ってみたらずしりと重い。「これをかついで、雪道を金山駅まで往復五十キロ、歩いて行って来い。」と言われたらさぞ途方に暮れてしまう事だろう。このトビをかついで歩く十歳の平岡少年の心の不安と、たくましさ。六十年前の雪の峠道に思いを馳せた。(2003年2月取材)
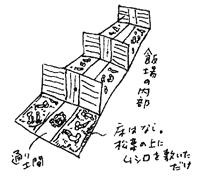

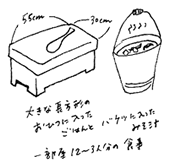
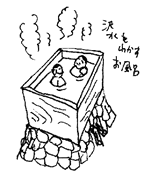







-冬--300x300.jpg)
